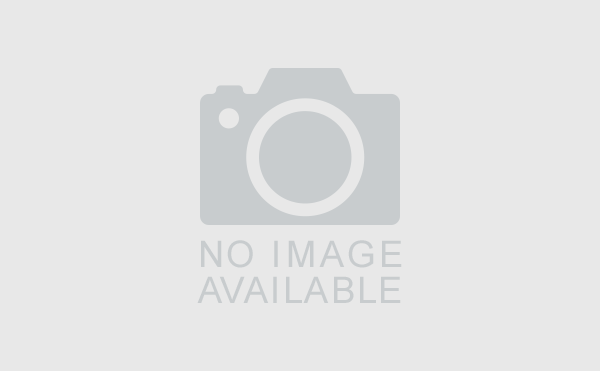【松山市議会議員 ひがき良太】 9月定例会一般質問②
昨日、松山市議会9月定例会において一般質問に登壇致しました。
【多発する自然災害への本市の対応】について、以下の事項を質問致しました。
①避難情報に基づく速やか避難行動を促すべく市民の避難情報の認知度調査を行うべきと考えるが、必要性の所感について
私の所感について
平成30年7月に発災した西日本豪雨災害での出来事は、記憶に新しいことかと存じます。
大雨特別警報が11府県に発表される記録的に大雨により、本市、そして県内において河川の氾濫・土砂災害が多数発生し死者・行方不明者を出す大惨事となりました。
その後の教訓として、「住民が自らの命は自ら守る意識を持って自らの判断で避難行動をとり、行政はそれを全力で支援をするという住民主体の取組強化による防災意識の高い社会を構築する」必要性が示されました。
こうした教訓が後押しし、本市では、「自らの命は自ら守る」という意識の徹底や、地域の災害リスクととるべき避難行動等について住民の理解を促進するため、住民主体の取組を支援・強化することにより、社会全体としての防災意識の向上に努めてまいりました。
しかしながら、「自らの命は自らが守る」という防災意識の向上は十分であるとはいえません。
そして近年多発する自然災害により、行政による避難情報や避難の呼びかけが分りにくいとの課題や、タイミングや避難場所等広域避難の困難さが顕在化しております。
年明けの通常国会において災害対策基本法改正案を提出し、災害時に市区町村が発令する避難勧告を廃止し避難指示に一本化する方針を明らかにしました。
これまで避難勧告を出していたタイミングで避難指示を出し、避難指示が出るまで動かず逃げ遅れてしまう事がない様にするものです。
制度変更をいかに広く周知し避難情報の意味を住民の方に理解してもらうことが必要不可欠であり、避難情報が避難行動に結び付けなければなりません。
近年、猛威を増している自然災害に単なる制度変更というだけでなく本市としても柔軟な対応をしていかなければなりません。
しかしながら、台風19号被災地の住民を対象とした内閣府の調査によると、避難勧告と避難指示の意味を正しく理解していたのは18%にとどまっております。
新制度に移行する前でも、現行制度下の中でも避難情報を正確に把握して頂くことは、その後の速やかな避難行動に繋がります。
避難情報がどんなに精緻で発信の多様性に富んでいたとしても、理解されていなければ避難行動には結びつかないのです。