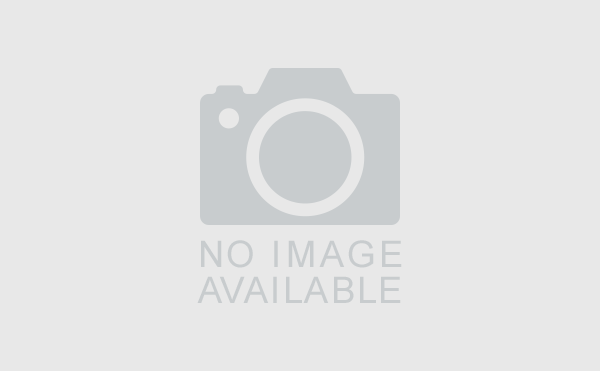【松山市議会議員 ひがき良太】 9月定例会一般質問①
昨日、松山市議会9月定例会において一般質問に登壇致しました。
【松山市SDGs推進協議会】について、以下の事項を質問致しました。
- 松山市SDGs推進協議会規約第三条三項における協議会の活動について「環境モデル都市まつやまの推進に関すること」とした理由について
- 全員参加で「持続可能な地域」の実現に向けて、本市におけるSDGsの取り組みにローカリズムの視点を取り入れ地域に落とし込む必要があると考えるが、松山市SDGs協議会におけるローカリズムへの認識と今後の展望について
- 中島で創った「環境に優しい電力」を道後などで活用してもらうツールとしてグリーン電力証書事業を取り上げているが、事業の裾野を広げる今後の展望について
- スマートアイランドモデルに関する先行分科会で、にぎわい創出におけるブランド定義を地域住民も含めて行う考えがあるか否かについて
- スマートアイランド構想の細部に今後サービスが拡充される5Gすなわち第5世代移 動通信システムにのせた新文明技術の活用等について挙げられていませんが、遠隔診療や 生活における課題解決のソリューションとして、ロボティクスやモビリティ、AR(拡張現実)、VR(仮想現実)、ドローンなどの幅広い領域をカバーする最先端テクノロジーを活用した中長期的な戦略を持っているのかについて
私の所感について
本市では、全員参加で「持続可能な地域」を創るをコンセプトに、
「すべての人が現状に満足し幸福を感じられる地域」
「満足感と幸福感が、社会的に適応しながら、今後も続いていくと確信できる地域」
の二つを両立することを目的に松山市SDGs推進協議会の設立がなされました。
目的遂行の為、そこに生きる地域住民自らの力で課題を洗い出し、分野とテクノロジーを掛け合わせたイノベーションによりアプローチしていくのが在るべき姿だと思います。
その過程における行政の役割とは、橋渡しであり背中を押すことです。
決められたスキームを念頭に、行政による主体の誘導はSDGsの本旨に反することとなります。
それ故に、行政が取るべきポジショニングとは、非常にセンシティブな判断が必要とされます。
本協議会において、産・学・民・官・金等の多様な主体が一堂に会し、共通認識のもとでパートナシップを形成し地域課題へアプローチしようとする空間を創出したことは、きっかけづくりとしての大きな成果といえるでしょう。
しかしながら、産・学・民・官・金等の主体に決定的に欠けているのはローカリズムの発想です。地域住民不在の主体には、体系的なマーケティング調査やツールやスキームの開発には優れている一方で、真に向き合わなければならない地域の課題が霞むのではないかと危惧しております。
住み続けたいと思える地域にという観点からいうと持続性に欠けるのではないでしょうか。
産・学・民・官・金等の皆様が、それぞれSDGsに挑戦される事は素晴らしい事です。
ただ、全員参加で「持続可能な地域」を謳っている以上は、幸福感や満足感を阻害する地域課題の洗い出しは地域住民によるものでなければならないですし、その解決方法としてのツールを創る、つまり分野とテクノロジーを掛け合わせたイノベーションという局面で産・学・民・官・金の出番ではないでしょうか。場合によっては、地域住民自らが解決方法のツールを導きだす事も然りです。
令和2年7月31日に開催された「松山市SDGs推進協議会 キックオフ総会」において配布された資料「松山市SDGs推進協議会の仕組みについて」の中で、人材発掘・人材確保として、地域・企業からのESG投資とボランティアと記載されております。
しかしながら、ESG投資は環境・社会・企業統治に配慮した高い倫理性を持った企業の存在と同時に投資家の理解が求められます。
ボランティアも同様で、明確な課題設定があって初めて「助けになりたい」「ほっとけない」「社会勉強」等々の動機が生まれ行動するのです。
そこには、相互理解が必要不可欠ですし、関係人口を増やす取り組みが鍵となります。
ですが、その担い手は金融機関、県外企業、松山市SDGsサポーターズクラブとなっており地域住民不在となっております。地域課題解決のための自律的好循環を形成する取り組みに地域住民は欠かせません。
本推進協議会規約の中身に目を通すと、松山市環境モデル都市行動計画が下地にあり、地域課題の洗い出し及びその解決方法に対しては既に既定路線がある様にも見受けられます。
行政課題を解決する民間事業への流れではなく、地域が抱える課題を解決する松山市SDGs推進協議会であって欲しいですし、推進協議会にはイノベーションを期待します。
松山市SDGs推進協議会が行政施策補完団体の様な印象も受けます。
松山市SDGs推進協議会の先行分科会としてスマートアイランド構想に関する分科会設置、現在活動中だと伺っております。
暮らしの質の向上と防災力強化という中島の地域課題に即し太陽光エネルギーの地産地消と電動モビリティの活用を促進することでブランド力の向上と中島を魅力発信のコンテンツを増やしていこうという取り組みです。
市内回遊を促すメニューとリンクをさせることで取り組みが実を結び経済循環とにぎわい創出に繋がり、それが地域に還元されていくスキームとなっております。
本事業のメリットは、販売収入を21世紀松山創造基金へ入金し新たな太陽光発電設備導入経費への充当や環境教育に活用されることです。
そして、購入者のメリットは、通常購入する電気を自然エネルギーで発電したとみなせることから環境貢献へのPRに繋がります。しかしながら、購入者のメリットを存分に発揮するには周りの厳しい目があって初めて評価の対象となり得るのです。
グリーン電力証書、それ程知名度もなく知らない人がほとんどではないでしょうか。
購入者になって頂く営業努力とともに、購入者の周囲に然るべき評価を頂くために知って頂く機会が何よりも大切なのです。そうでなければ、市場としての成長とブランド力は見込めないのではないでしょうか。
太陽光発電やEV充電設備、ソーラースタンド、グリーンなモビリティの島内活用により発生した「環境に優しい電力」をグリーン電力証書事業を通じて市場に広げることがブランド力の向上に繋がるのか。
その事についてよくよく考えて頂ければなと思います。
環境に配慮するということは、社会資源を守り磨く行為であり、暮らしを守る行為です。
そこにグリーン電力証書をリンクさせることで経済循環がなされる、その事についてはよく理解できます。
しかしながら、グリーン電力証書を駆使し「環境に優しい電力」を広げることがブランド力向上に繋がり、他のメニューとパッケージすることでにぎわいを創出出来るとは思えないのです。ブランド力向上を謳うのであれば、まず地域住民の皆様と中島の強みと今後のブランディング戦略について話し合われるべきだと思います。「環境に優しい電力」で中島のブランド力が向上し人を呼び寄せられますでしょうか。
豊かな自然環境を始めとする貴重な社会資源、そこに住まう地域住民と繋がりが、他の何物にも代え難いブランドではないでしょうか。
住み続けたい中島をコンセプトにするのであれば、スマートアイランド構想で示されるスキームも多少は理解できます。しかし、そこに更なる経済循環やにぎわい創出を生み出したいのであれば戦略性に乏しいと言わざるを得ません。
「環境に優しい電力」以外にも、中島には誇れるものがたくさんあるのです。
先ず私は、SDGsを地球上に生きる人類が取り組む「テーマ」ではなく、超えなくては ならない「ハードル」として、従来の経済を基盤とした開発ではなく、地球環境の保護及び 共存を社会基盤とした Future デザインを各産業及び一般社会が創造しなくてはいけない 時代であると考えております。
内閣府地方創生推進事務局から松山市がSDGs未来都市・自治体SDGsモデル事業 に選定されたことで先駆的な取組に挑戦し、年齢、性別、能力などのいかんにかかわりなく、すべての人が安心して暮らすことができ、また、個々の持てる能力を最大限に発揮して、自己の存在を誇らしく感じることができるユニバーサル社会の実現にむけて議員の立場でも 政策として考察していく所存です。
そこでSDGsの趣旨にのっとり、「誰一人取り残さないまちづくり」を松山市が推進さ れることを大前提として中長期的な企画戦略を如何にターゲット化されているのかをお尋 ねさせていただきます。
SDGsは「持続可能」「誰一人取り残さない」「パートナーシップ」という理念のも と、社会・環境・経済の課題に対して、統合的に相乗効果が生まれるよう、バランスよく取 り組むこととされています。
こうした社会・環境・ 経済面での相乗効果により、持続可能 な発展を目指す考え方は、まちの好循環の維持・拡大に資するものであり、今後のまちづく りの推進に当たっては、SDGsの基本理念を一層市民サービスに反映していくことが重 要であると強く考えております。
一部分野を抽出すると、医療・教育分野における5G文明 は止まることを知らず、グローバル社会では瞬く間に拡充して行くことでしょう。先にあげましたスマートアイランド構想の舞台となる中島地区は離島です。
その中島地 区は高齢化率65%であり、近年は異常気象に伴う自然災害が多発しております。第5世代 移動通信システムを効果的に活用することで救助ドローンによる救助活動、立体的な遠隔 診療の実現、AIを活用した第一次産業の振興等、これらの課題解決によって数多くのター ゲットを必然的に達成することができ、より多くの市民を誰一人取り残さない公共サービスの充実を図ることができると考えます。